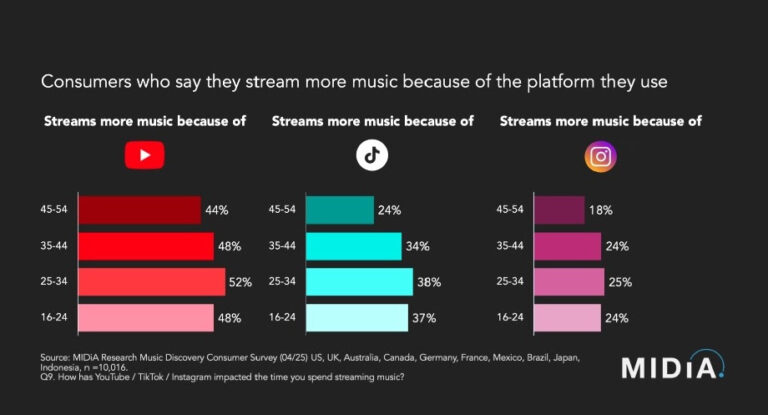
アーティストの楽曲がSNSでバイラルヒットすれば、
https://www.midiaresearch.com/
同社は音楽発見の行動について1万人以上を対象に調査を実施。
「
SNSで聴いた楽曲をストリーミングサービスで再生しない理由で
MIDiAは、ショート動画プラットフォームで流れる楽曲が、
最も人気の音楽発見のプラットフォームはYouTubeで、
一方、楽曲のバイラル化が再生数や保存数の増加させるのは、
とりわけ、MIDiAの報告では、
シリサーノは、SNSや楽曲バイラル化と再生の関係性について、
問題を深刻化しているのは、SNSアプリの構造だ。
一方、SNS各社は、
音楽発見を促進する機能の開発や連携強化を図るSNS各社に対し
